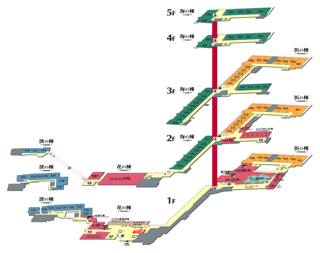[PR] 本ブログの商品紹介リンクには広告が含まれています
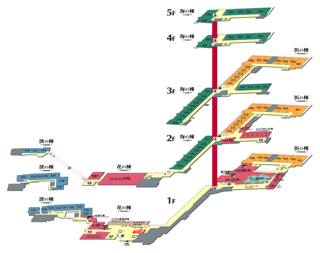
図は本文とは関係ありません
とある非営利団体のWebサイトのメンテをしているのですが、このサイトが実にひどいことになっているのです。
そのサイトは、たぶん20世紀の終わり頃ボランティアのアマチュアの方がFront PageとかHome Page Builderのようなツールを使って原型を作って、それを毎年順送りでこれまたボランティアの方が担当を引き継いで今までメンテをしてきたものなのですが、まるで増改築を繰り返した田舎の温泉旅館のように、サイトの利用者にとっても、サイトの管理者にとっても、どこになにがあるのか分からない状態になっています。破綻をきたした要因はいくつかあるのですが、主なものはこんなところ。
- サイト内のディレクトリ構造のルールがなく、たとえばHTMLファイルで使うグラフィックファイルの場所が担当した人の好み(と、その時使っていたツールのデフォルト値)によってばらばら
- ページのゾーニングのルールがなく、ページ内のナビゲーション要素などもまるで一貫性がない(というか、ナビゲーション要素がまったくない、袋小路のようなHTMLページだらけ)
- 使っていたオーサリングツールのせいで、ページの中のHTMLもぐちゃぐちゃ。代々の担当者が文字修飾を編集した痕跡で<font>や<b>やらが開いたり閉じたりしていて、なにがなにやらわけがわからない
- おまけに、サイトの機能を強化するために思い思いに作られた各種スクリプトは、クロスサイトスクリプティングやらディレクトリトラバースなど、典型的な脆弱性だらけ
でも、程度の差はあれ、こういうサイトをよく見かけます。きっと、こうなってしまう共通の理由があるんじゃないかと思うのです。
Webサイトなんてのは、作ったらそれで終わりではなくて、作ったページやナビゲーションなどが将来のサイト構造に引き継がれていく、まさに“Going Concern”でなければなりません。その点、新聞や雑誌のように毎号作りきりというより、歴史的建造物に近い方法で継承することが期待されます。
たとえば神社のようなものを想像してみるとわかりますが、歴史的建造物は「屋根は切妻」とか「床は高床」とか「梁の長さはこれだけ」とか「扉の形はこうで、このように開く」といった様式が厳しく決まっていて、しかも宮大工さんがその様式を厳密に守って作業するので、後の世代が建て増しをしても昔の建物と新しい建物がちぐはぐになることはありません。ところが、同じ宗教の建造物でも様式やルールなしに担当者が思い思いに必要な機能要素を継ぎ足して作った「なんとかサティアン」は見事にグロテスクな構造物になっていたのはご存じの通り。
Webサイトの場合も、ページのゾーニング、ディレクトリ構造、グラフィックのトーンなどをきっちり定義して様式を固め、その様式をテンプレートとして管理できるツールを使って維持すれば、制作者が入れ替わっても土台が崩れることはなく、長く運営したからといって構造が破綻することはありません。ところが建造物と違ってWebサイトは特に訓練を受けなくても誰でもそれらしいものを作ることができますから、安易に「自主管理で、担当者がよいと思うように運営を引き継いでよろしい」なんてことになりがちで、その結果前述のようなグロテスクなサイトができあがってしまうわけです。
その点、ブログのシステムのようなCMSが簡単に使えるようになったことは、これのおかげで、サティアンみたいなサイトがどれだけ排除されたかと思うと、Webの発展にとっては大変意義があることだと思ったのでありました。小さいことだけど、偉大な発明だったんだな、これは。